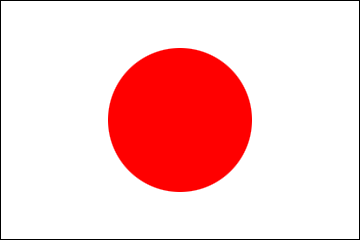浦潮だより:総領事クラブ
令和7年10月8日
浦潮だより:総領事クラブ
令和7年10月8日
外交官の仕事の一つは人脈形成。相手国要人との関係構築はもちろん、各国外交官との横のネットワーク作りも大切です。しかしながら現在、G7で在ウラジオストク総領事館を持っているのは日本だけ。韓国総領事館とは緊密に協力していますが、ほかに頼りになるのはインドやウズベキスタンの総領事です。今年、ウズベキスタン総領事の発案で「総領事クラブ」と称する定例懇親会が立ち上がりました。ロシア沿海地方外交代表を交えて、各国総領事と幅広く雑談ができるので、大変助かっています。
振り返ってみると、ワシントンDCでは、米国政府やシンクタンクとの接触が日常的に忙しく、各国外交官との付き合いは補助的な位置づけでした。モスクワでは、米国、英国、ドイツの外交官から得る情報が特に有益だったと記憶します。ミンスクでは、ベラルーシの隣国であるポーランド、リトアニア、ウクライナの外交官が情報通でしたし、ドイツ大使館やEU代表部の分析も鋭くて参考になりました。
面白いことに、豪州・キャンベラでは外交団情報にユニークな濃淡がありました。まず、ニュージーランド外交官は、豪外務貿易省に深く入り込み、豪州人とほぼ一緒に仕事をしているので、最も内部事情に通じています。次いで豪州の同盟国である米国、旧宗主国の英国。その次に「準同盟国」の日本がフランスやドイツと並んで深く食い込んでいました。また、トンガやサモア、ソロモン諸島といった太平洋島嶼国がキャンベラで大きな存在感を発揮しています。豪州はニュージーランドとともにPIF(Pacific Islands Forum)のメンバーであり、太平洋島嶼国と緊密に協力しているためです。PIFは、「ファミリー・ファースト」という原則を掲げ、地域の安全保障問題は、まずファミリーたるPIFで協力して解決することを目指しています。私の在勤時は、福島原発ALPS処理水の海洋放出が島嶼国との間で大きな緊張を招きかねない時期でした。豪州との意思疎通、島嶼国の外交官から得る情報が、日本外交にとって大変に貴重でした。
 日本チーム
日本チーム
 国際親善サッカー大会開会式
国際親善サッカー大会開会式
さて、話をウラジオストクに戻します。当地ではG7の公館がないため、別のネットワークを構築する必要があるのですが、その一つがインド、ウズベキスタン、キルギスといった親日的な国との連携なのです。8月にはウズベキスタン総領事がウズベキスタン独立34周年を記念して、第一回国際親善サッカー大会を主催してくれました。ロシア沿海地方、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギスタン、中国、韓国、インド、ベトナムと並んで、日本も急拵えの邦人チームで参加しました。各国は普段から趣味でサッカーを楽しんでいるチームが母体となっているため、揃いのユニフォームでビシッと決めていましたが、日本はとっさのことで間に合わず、思い思いの自由服でした。結果は、インドに0-4、タジキスタンに0-8で敗北し、惜しくも予選敗退。せめて1点は取りたかったところですが、皆さんよく善戦してくれました。ちなみに決勝はタジキスタンがウズベキスタンを破って優勝しました。日の丸を背負って戦うからには、来年こそ事前にユニフォームを揃えて、せめて1勝を挙げたいと思っています。
 在豪フランス大使館次席の送別会にて:キャンベラの仲間
在豪フランス大使館次席の送別会にて:キャンベラの仲間
最後にもう一つ。キャンベラでは、Dグループという集まりが自然にできました。ドイツ外交官、ニュージーランド人有識者と私の3人でドイツビール店に飲みに行ったのが発端で、気の合うフランスやオランダの大使館次席にも声をかけ、月に一回くらいのペースで会食するようになりました。人事情報や裏話を含めて雑多な情報交換を重ねるうち、お互いを励まし合う友達になり、大使館次席(Deputy)がほとんどなのでDグループと自称。国は違えど、同年代の中間管理職の悩みは同じです。今はパリ、アムステルダム、キャンベラ、ウラジオストクと勤務地が分かれましたが、グループチャットでエールを送り合っています。いつまでも大切にしたい仲間です。
T.M.