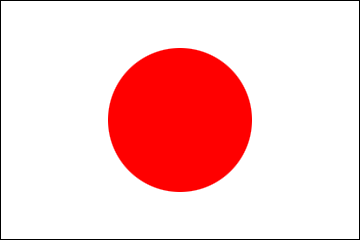浦潮だより:ビールの交差点
令和7年2月14日
 熊ビールで乾杯!
熊ビールで乾杯!
浦潮だより:ビールの交差点
令和7年2月14日
ロシアと言えばウォッカ、と思う方が多いでしょうが、なかなかどうして、ウラジオストクは「ビールの交差点」と名付けたいくらいです。仕事のお付き合い先ではウォッカを勧められることが少なくありませんが、50代も後半に入った身にとっては肝臓も大事。ロシアではむしろビールを飲んでいます。どこのスーパーでも、多種多様なビールが手頃な価格で売っていて、ロシア、チェコ、中国、そして日本の銘柄がずらりと並びます。まるでスクランブル交差点のようです。
 搾りたての生ビールをタップで
搾りたての生ビールをタップで
ロシア・ビールでは、特に「スターリー・メリニク」(古い風車という意味で、風車の絵がトレードマーク)が私のお気に入り。大型スーパーでは、大きなペットボトルに生ビールを注いでもらう方式が豪快です。街中にも生ビールをタップから注いで売る専門店があります。
最近、はまっているのは「ハルビン・ビール」。ハルビンのビール工場はかつてロシア人が作ったことから、今もロシア風のテイストで生産されているそうで、すっきりした飲み心地と苦みが絶妙のバランスです。一方、日本でもよく見かける青島ビールは、ドイツ人が建てた工場でドイツ風に製造されていると聞きました。ハルビンはウラジオストクから飛行機でたった1時間の距離ですから、いつか訪ねてみたいと思っています。
ちなみに、ロシアで大変人気のある作家・安部公房は、満州国の奉天市(現・瀋陽市)で育ちました。終戦間際に東京大学から奉天に戻り、そこで戦後の混乱に巻き込まれたそうです。昨年、安部公房生誕100周年を記念して同氏の著作が次々と電子書籍化されたおかげで、ある新聞記事で紹介されていた「けものたちは故郷をめざす」を読むことができました。戦後の大混乱の中、満州で孤児になった主人公が死線を越えて日本を目指すストーリーで、中国東北部の厳しい自然環境を背景に生々しく描かれています。「もしかすると、日本なんて、どこにもないのかもしれないな…」という主人公の言葉がぐっと胸に迫りました。
最近、はまっているのは「ハルビン・ビール」。ハルビンのビール工場はかつてロシア人が作ったことから、今もロシア風のテイストで生産されているそうで、すっきりした飲み心地と苦みが絶妙のバランスです。一方、日本でもよく見かける青島ビールは、ドイツ人が建てた工場でドイツ風に製造されていると聞きました。ハルビンはウラジオストクから飛行機でたった1時間の距離ですから、いつか訪ねてみたいと思っています。
ちなみに、ロシアで大変人気のある作家・安部公房は、満州国の奉天市(現・瀋陽市)で育ちました。終戦間際に東京大学から奉天に戻り、そこで戦後の混乱に巻き込まれたそうです。昨年、安部公房生誕100周年を記念して同氏の著作が次々と電子書籍化されたおかげで、ある新聞記事で紹介されていた「けものたちは故郷をめざす」を読むことができました。戦後の大混乱の中、満州で孤児になった主人公が死線を越えて日本を目指すストーリーで、中国東北部の厳しい自然環境を背景に生々しく描かれています。「もしかすると、日本なんて、どこにもないのかもしれないな…」という主人公の言葉がぐっと胸に迫りました。
 パンダ柄のベルギービール?!
パンダ柄のベルギービール?!
また、歌手の加藤登紀子さんはハルビン生まれ。お父様が帰国後に開店したロシア料理店「スンガリー」は、今も多くの人に愛される老舗です。先日の浦潮だよりでご紹介したズベニャツキー・ゴーリキー劇場監督も、「スンガリー」で何度も食事したと話していました。
そういったエピソードを思い出しつつ、ハルビン・ビールを味わっています。
そういったエピソードを思い出しつつ、ハルビン・ビールを味わっています。
 生ビールの注ぎ売り
生ビールの注ぎ売り
 多国籍ビールがひしめく売り場
多国籍ビールがひしめく売り場
ウラジオストクでは、ドイツビールやチェコビールの銘柄も売っていますし、地元の人は日本のビールのことが大好きです。もう一つ、個人的に嬉しいのは、ベラルーシ・ビールの「リーツコエ」が買えること。ウラジオストクで飲むと少し味が薄い気がしますが、2年半勤務したミンスクで慣れ親しんだ味は、何とも懐かしい気がします。
一方、残念ながら当地では手に入らないビールもあります。前任地の豪州キャンベラでは、Capital Brewing Co. のペールエールがお気に入りだったのですが、そういったクラフトビールはもちろんありません。日本ビールの味も、一時帰国の折に味わうのとは、やはり違う気がします。かつてビールメーカーの知人から伺った話では、外国で現地生産しているビールは、日本産とはどうしても味が異なるため、本社の試飲でいつも指摘を受けているとか。
とはいえ、「今、ここ」を大切に過ごすことが幸せの鍵です。これからも、ウラジオストクならではの味を見つけていきたいと思います。
一方、残念ながら当地では手に入らないビールもあります。前任地の豪州キャンベラでは、Capital Brewing Co. のペールエールがお気に入りだったのですが、そういったクラフトビールはもちろんありません。日本ビールの味も、一時帰国の折に味わうのとは、やはり違う気がします。かつてビールメーカーの知人から伺った話では、外国で現地生産しているビールは、日本産とはどうしても味が異なるため、本社の試飲でいつも指摘を受けているとか。
とはいえ、「今、ここ」を大切に過ごすことが幸せの鍵です。これからも、ウラジオストクならではの味を見つけていきたいと思います。