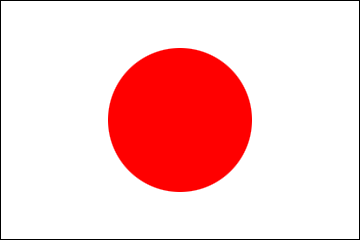ダニ媒介脳炎について
平成27年6月16日
2015年6月16日
在ウラジオストク日本国総領事館
<概要>ダニ媒介脳炎は、ロシア極東から中央ヨーロッパにかけての広い範囲で発生するウイルス感染症です。いくつかの亜型があり、主な発生地域によってロシア春夏脳炎、中央ヨーロッパ脳炎などと呼ばれることもあります。また、初夏に発生することが多いので初夏脳炎と呼ばれることもあります。
ウイルスを持っているマダニに咬まれることによって感染しますが、まれにウイルスに感染したヤギや羊などの生乳を介して感染する場合もあります。沿海地方でマダニが脳炎ウイルスを持っている割合は約2%です。また、沿海地方での患者発生数は年間十数人~数十人で、人口10万人当たりの平均年間患者発生数にすると約2.2人となっています。
<症状・治療>
感染後数日~2週間程度の潜伏期を経て、発熱、頭痛、吐き気、筋肉痛、倦怠感などの症状が現れ、その後脳炎に進展して痙攣や意識障害などの症状が現れます。脳炎ウイルスに対する特異的な治療薬はなく、治療としては対症療法や合併症の管理などが行われます。沿海地方における発症者の致死率は約7%で、回復しても麻痺などの後遺症が残る場合があります。
<マダニの吸血>
マダニは体長数ミリメートル程度の8本足の節足動物で、肉眼で確認できます。動物の血液を唯一の栄養源としており、森林、牧草地や草木の生い茂った場所など、野生の動物が出没するような場所に生息しています。通りかかる動物の呼気、体温、振動などを感知すると、葉や茎の端で前足を広げた姿勢で待ち構え、動物が触れると前足を引っかけて素早く乗り移ります。その後しばらく皮膚の上を歩き回り、吸血に適した場所を見つけると皮膚を咬みます。そして、唾液腺からセメント様物質を分泌して口器をしっかりと皮膚に固定し、そのまま数日間吸血し続けます。一般的に、咬まれるときや吸血中に痛みは感じません。
沿海地方でマダニが吸血活動を行うのはおおむね4月の初めから10月ごろまでで、この間毎年数千人がマダニに咬まれたとのことで医療機関を受診します。咬まれる人数が特に多いのは、5月から6月にかけてのまだ比較的涼しい時期です。
<マダニに咬まれた場合>
皮膚を咬んでいるマダニは、軽く引っ張ったぐらいでは取れません。マダニを離れさせるために油やアルコールをかける、火を近づけるなどの方法が紹介されていることがありますが、確実で推奨される方法はありません。また、無理に引っ張ると頭部がちぎれて皮膚に残ってしまうことがあります。
きちんと全体を取り除くためには、皮膚を咬んでいる根元を先の細いピンセットや毛抜きのような器具などでつかんで慎重に引き抜く必要がありますが、なるべく医療機関を受診して取ってもらったほうがよいでしょう。取り除いたマダニは、干からびたりしていなければウイルスを持っているかどうかの検査が可能で、その後の経過観察方針の参考となります。
当地では、マダニに咬まれた後に発症予防として免疫グロブリン製剤が使われることがありますが、世界的にはその有効性や安全性に対する評価は定まっていません。マダニに咬まれた後数週間は体調の変化に注意し、異常を感じた場合には医療機関を受診してください。
<予防>
当地のマダニは、ダニ媒介脳炎のほかにも、ライム病、アナプラズマ症、エールリキア症などを媒介することが知られています。治療薬がなく予後が深刻であることから脳炎が最も重要ですが、様々な感染症を予防する観点から、マダニに咬まれないようにすることが最も基本的な予防となります。マダニが生息しているような場所に立ち入る場合には、肌の露出が少ない服装や帽子の着用を心がけるようにしましょう。また、時々自分や同行者の体、あるいは持ち物やペットにマダニが付いていないかどうかを確認するようにしましょう。
ダニ媒介脳炎に対しては予防接種が有効で、95%以上の予防効果があるとされています。当地では、ロシア製のほかオーストリア製やドイツ製のワクチンが流通しており、それぞれ接種スケジュールが若干異なっていますが、いずれも3回の接種が基本です。2回目の接種は1回目の約1~数か月後で、2回目の接種から2週間程度で免疫が有効になります。そのままだと1年程度で徐々に免疫が低下しますが、1回目の約1年後に3回目の接種を受けると、その後3年以上免疫が持続します。その後は3~5年(製品や年令により異なる)ごとに1回追加接種を受けると免疫が維持されます。なお、日本ではダニ媒介脳炎のワクチンは未承認ですが、一部のトラベルクリニックでは輸入ワクチンを用いて予防接種を実施しています。
<その他>
当地で予防接種を受けられる医療機関やマダニの検査を受けられる医療機関などについては、当館ホームページの医療機関リストでもいくつか紹介しておりますので、参考にしてください。また、ダニ媒介脳炎については、厚生労働省や国立感染症研究所のホームページも参考にしてください。
○当館ホームページ:当地医療機関リスト
https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000029.html
○厚生労働省:ダニ媒介脳炎に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/mite_encephalitis.html
○国立感染症研究所:ダニ媒介性脳炎とは
http://www.nih.go.jp/niid/ja/encycropedia/392-encyclopedia/434-tick-encephalitis-intro.html